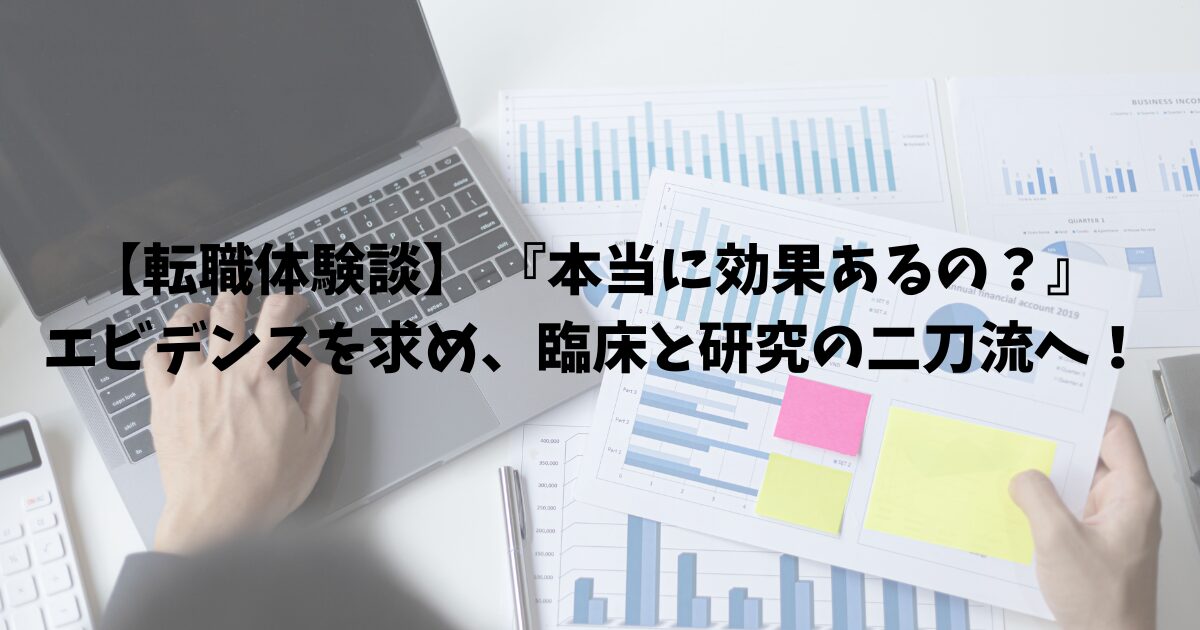本記事は、臨床経験10年目の中堅理学療法士が、日々の臨床で感じた「この治療法は本当にベストなのか?」という疑問を原動力に、エビデンス(科学的根拠)を追求する道へ進んだ転職体験談です。
慣習的な治療への葛藤から、EBM(根拠に基づく医療)の重要性に目覚め、臨床と研究の「二刀流」が可能な病院へ転職するまでの経緯と、転職後のリアルな日常、研究が臨床にもたらした具体的な成果を語ります。
転職を考えている理学療法士の方々へ、自身の探求心をキャリアに繋げる一つの選択肢として、具体的な道筋と可能性を提示します。
本記事では、個人や施設の特定を避けるために創作を交えています。
転職前の葛藤:日々の臨床で感じた「なぜ?」
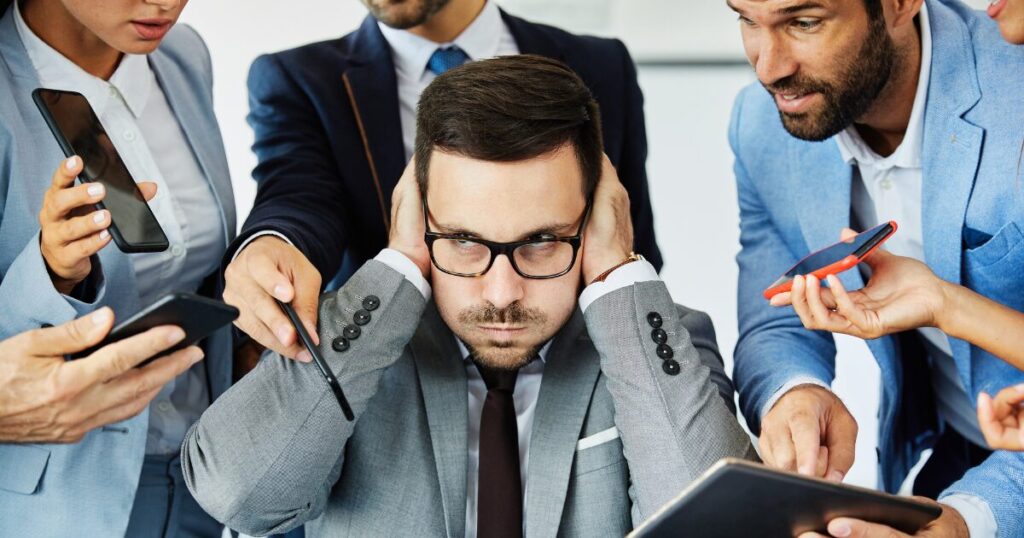
経験則と慣習だけでは越えられない壁
 エル
エル佐伯徹、33歳。理学療法士として10年目の春、僕は大きな壁にぶつかっていました
私が勤務していた整形外科クリニックでは、日々のリハビリテーション業務に追われる毎日でした。
先輩から引き継いだ治療プロトコル、昔から慣習的に行われている手技。それなりに経験を積み、後輩指導も任される立場になりましたが、心のどこかで拭えない疑問が渦巻いていました。
 エル
エル本当にこれが、この患者さんにとってベストなのだろうか?
同じ診断名の患者さんでも、治療効果には個人差がある。その差は一体どこから来るのか。私の頭の中は「なぜ?」で溢れかえっていました。
感覚や経験則に頼るだけのリハビリに、限界を感じ始めていたのです。患者さんの貴重な時間と人生を預かる専門職として、もっと確かなものを提供したい。その思いが、日に日に強くなっていきました。
EBM(根拠に基づく医療)との出会いが拓いた道
そんな葛藤の中で、私にとって転機となったのが「EBM(Evidence-Based Medicine)」との出会いです。
日本語では「根拠に基づく医療」と訳され、最新かつ最良の科学的根拠、医療者の専門的経験、そして患者の価値観を統合し、治療方針を決定するアプローチを指します。
きっかけは、ある週末に参加した勉強会でした。 そこで、海外の最新論文を引用しながら、ある治療法がいかに効果的かをデータで示している発表に衝撃を受けました。
「これだ!」と。自分の臨床を客観的に評価し、常に最新の知見を学び続ける必要性を痛感した瞬間でした。 しかし、日々の業務に追われる中で、論文を読み解き、臨床に応用していく時間はなかなか確保できません。
 エル
エル患者さんのために、本当に効果のあるリハビリを提供したい!
この純粋な思いを実現するためには、今の環境を変えるしかない。そう決意するのに、時間はかかりませんでした。
転職への決意:臨床と研究の「二刀流」という選択

大学院進学か、研究特化型の病院への転職か
EBMを実践するためには、研究的な視点とスキルが不可欠だと考えた私は、具体的なキャリアチェンジを模索し始めました。 選択肢は大きく分けて二つ。
- 働きながら大学院(博士課程)に進学する
- メリット:現在の臨床現場を離れずに研究手法を学べる。
- デメリット:学費の負担が大きい。業務と学業の両立が極めてハード。
- 研究に力を入れている病院や施設へ転職する
- メリット:給与を得ながら研究活動に時間を使える環境がある。
- デメリット:求人数が限られる。臨床経験が中心だった自分が、研究能力をアピールできるか不安。
大学の恩師に相談したところ、臨床業務と並行して研究活動を行えるよう「研究日」を設けている病院や、施設内に研究所を併設している医療法人が存在することを教えていただきました。
 エル
エル臨床現場で感じた疑問を、自分で研究して明らかにしたい。
そして、その成果をまた臨床に活かしたい。
私にとって、臨床と研究は切り離せるものではありませんでした。この二つを両立できる環境こそが、理想の職場だと確信したのです。
私が「研究日」のある病院を選んだ理由
最終的に私が選んだのは、週に1日の「研究日」が制度として確保されている回復期リハビリテーション病院への転職でした。この選択に至った理由は、以下の3点です。
- 臨床と研究のサイクルを回せる理想的な環境:臨床で生まれた疑問をすぐに研究テーマとして設定し、研究で得た知見を目の前の患者さんに還元できる。 このスピード感と相乗効果は、最高のモチベーションになると感じました。
- 経済的な安定:大学院進学と異なり、給与を得ながら研究に没頭できる点は大きな魅力でした。生活の基盤を安定させながら、新たな挑戦に踏み出せる安心感がありました。
- 組織としてのサポート体制:研究活動が個人の努力だけでなく、組織として推奨されている文化がありました。指導経験豊富なドクターや、同じ志を持つセラピストと議論できる環境は、一人で学ぶ以上の成長をもたらしてくれると期待しました。
転職活動では、これまでの臨床経験に加え、「なぜ研究に取り組みたいのか」という強い動機と、臨床現場で感じてきた具体的な課題意識を熱意をもって伝えました。幸いにもその思いが伝わり、私は臨床家であり研究者でもあるという、新たなキャリアのスタートラインに立つことができたのです。
転職後のリアル:臨床と研究の相乗効果

研究が臨床にもたらす「深み」
転職後の毎日は、刺激的で充実しています。 例えば、私の1週間のスケジュールは以下の通りです。
| 曜日 | 午前 | 午後 |
| 月曜 | 臨床業務(患者担当) | 臨床業務(カンファレンス等) |
|---|---|---|
| 火曜 | 臨床業務(患者担当) | 臨床業務(患者担当) |
| 水曜 | 研究日 | 研究日 |
| 木曜 | 臨床業務(患者担当) | 臨床業務(患者担当) |
| 金曜 | 臨床業務(患者担当) | 院内勉強会・研究進捗報告 |
水曜日の研究日には、大学の図書館で文献を検索したり、研究室でデータ解析に没頭したりします。
研究活動を通して身についたクリティカル・シンキング(批判的思考)は、臨床でのアプローチをより洗練されたものにしてくれました。
例えば、ある患者さんに対して、漫然と従来のリハビリを行うのではなく、「この患者さんの背景を考えると、先行研究Aよりも論文Bのアプローチの方が適合するのではないか?」「評価指標として、Cを追加することで効果をより正確に測定できるかもしれない」といった仮説検証のサイクルを自然と回せるようになったのです。
臨床での経験が研究テーマに深みを与え、研究で得た知識や思考法が臨床の質を高める。この相乗効果を、日々実感しています。
具体的な研究とデータが示す「エビデンスの力」
現在、私が取り組んでいる研究テーマの一つが「脳卒中後遺症患者の歩行能力に対する、特定のフィードバックを用いた運動学習プログラムの効果検証」です。
具体的には、患者さんの歩行をモーションキャプチャで三次元的に捉え、そのデータを基に理想的な関節運動との差分をリアルタイムで視覚的にフィードバックするというものです。
この研究を進めるにあたり、以下のような図表を作成し、客観的なデータで効果を検証しています。
- 研究デザインのフローチャート 研究の信頼性を示すため、被験者をランダムに「介入群(新しいプログラムを実施)」と「対照群(従来のプログラムを実施)」に割り付け、効果を比較する「ランダム化比較試験(RCT)」のデザインを組んでいます。この流れをフローチャートで視覚化し、研究計画の妥当性を示します。
- 対象者の背景情報 両群の年齢、性別、発症からの期間、麻痺の重症度などに統計的な差がないことを示すための表です。これにより、「介入効果は、元々のグループの差ではなく、純粋にプログラムの違いによるものである」と主張できます。
- 介入前後での歩行速度の変化(棒グラフ) 介入群と対照群の、プログラム実施前と実施後(例:4週間後)の歩行速度を棒グラフで比較します。例えば、「介入群では平均歩行速度が0.2m/s向上したが、対照群では0.05m/sの向上に留まり、群間には統計的な有意差が見られた(p < 0.05)」といった結論を導き出します。
これらのデータに基づき、新しいリハビリテーションプログラムの有効性を客観的に証明することができました。 この研究成果は院内のリハビリテーションプロトコル見直しのきっかけとなり、実際に患者さんの回復が早まったり、QOL(生活の質)が向上したりする事例も出てきています。 エビデンスに基づいたアプローチが、治療効果の向上に直結することを実感できた瞬間でした。
未来へ:理学療法の発展とキャリアパス

学会発表と論文執筆という新たな挑戦
研究の成果は、院内にとどまらず、外部へ発信することでさらなる価値を持つと教わりました。
昨年は、初めて国内の理学療法学会で、自身の研究成果をポスター発表する機会を得ました。 全国の研究者や臨床家と活発に意見交換し、自分の研究を多角的な視点から見つめ直す貴重な経験となりました。
そして現在、その研究成果を専門誌に論文として投稿する準備を進めています。 論文執筆は、自分の研究を論理的に再構築し、客観的な事実として世に問う、非常に骨の折れる作業です。
しかし、「自分の研究が、理学療法の発展に少しでも貢献できるかもしれない」 。その思いが、私を突き動かしています。臨床一筋だった頃には想像もできなかったキャリアの広がりが、目の前にはありました。
転職を考える理学療法士へのメッセージ
かつての私のように、日々の臨床に疑問や葛藤を抱えている理学療法士の方は少なくないと思います。
その「なぜ?」という探求心こそが、あなたを次のステージへ導く、最も尊い原動力です。 理学療法は、まだまだ発展途上の分野であり、未解明なことが数多く残されています。
だからこそ、私たち一人ひとりが臨床現場でリサーチ・クエスチョン(研究的な問い)を持ち続け、それを追求していくことが、分野全体の発展に繋がるのだと信じています。
臨床と研究の二刀流は、決して楽な道ではありません。 しかし、臨床で生まれた疑問を研究で解き明かし、その成果をすぐに目の前の患者さんに還元できるサイクルは、何物にも代えがたいやりがいと喜びに満ちています。 その先には、患者さんの笑顔と、理学療法の明るい未来が待っているはずです。
もしあなたが今の働き方に悩んでいるのなら、勇気を出して一歩踏み出してみてください。
大学院への進学、研究機関への転職、私のように研究日を設けている病院への転職など、道は一つではありません。あなたのその知的好奇心と探求心は、必ずや明日の医療を創る力になります。