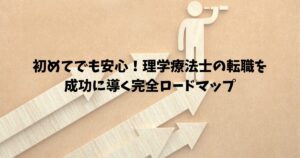本記事は、12年間情熱を注いできた理学療法士(PT)の仕事を、自身の慢性的な腰痛の悪化により断念せざるを得なかった一人の男性の転職体験談です。
臨床現場を離れるという苦渋の決断の後、彼は理学療法士として培った知識と経験を最大限に活かせる「福祉用具専門相談員」という新たな道を見つけ出します。
本記事では、彼がどのように挫折を乗り越え、新しい職場で専門性を発揮し、再び輝きを取り戻していったのかを、具体的なエピソードを交えながら詳細に綴ります。
身体的な負担の軽減だけでなく、家族との時間を取り戻し、新たなやりがいを見つけた彼の物語は、キャリアに悩むすべての医療・介護従事者にとって、次の一歩を踏み出すためのヒントとなるでしょう。
本記事では、個人や施設の特定を避けるために創作を交えています。
夢だった理学療法士の道、そして訪れた転機

患者さんの「ありがとう」が原動力だった日々
私が理学療法士という仕事に就いてから12年。急性期病院で8年、その後は地域に密着した訪問リハビリの世界で4年間、文字通り夢中で走り続けてきました。
理学療法士は、単に身体機能の回復を助けるだけでなく、患者さん一人ひとりの「その人らしい生活」を取り戻すための伴走者です。
脳梗塞で半身が不自由になった方が、再びご自身の足で歩いてトイレに行けるようになった時。ご家族が「先生のおかげです」と涙ながらに感謝してくださった時。その瞬間の喜びとやりがいは、何物にも代えがたいものでした。
特に訪問リハビリでは、病院という管理された環境とは違い、患者さんのリアルな生活空間に入り込みます。畳の部屋での立ち座り、狭い浴室での入浴動作、近所のスーパーへの買い物。生活のすべてがリハビリの対象であり、より深く、よりパーソナルな関わりが求められます。
患者さんやご家族と二人三脚で目標を立て、一つひとつクリアしていく過程は、この仕事の醍醐味そのものでした。この充実感こそが、私の原動力だったのです。
身体が発した悲鳴 – 無視できない腰痛の悪化
患者さんの生活を支えるという使命感に燃える一方で、私の身体は静かに悲鳴を上げていました。
特に、体重の重い患者さんをベッドから車椅子へ移す「移乗介助」や、長時間の前屈み姿勢でのリハビリは、腰に大きな負担をかけ続けます。若い頃は一晩寝れば回復していた痛みも、30代半ばを過ぎると慢性化し、常に鈍い痛みを抱えるようになりました。
騙し騙しコルセットで固定し、湿布を貼り続けていましたが、ある朝、ついに限界が訪れます。
いつものように患者さんを支えようとした瞬間、腰に激痛が走り、その場に崩れ落ちてしまったのです。診断は、重度のぎっくり腰(急性腰痛症)。
一週間、寝たきりの生活を余儀なくされました。「この身体では、もう患者さんを安全に支えることはできないのではないか…」。天井を見つめながら、これまで目を背けてきた将来への不安が、重く冷たい現実として目の前に突きつけられました。
情熱だけではどうにもならない身体の限界。それは、理学療法士としての私の存在価値そのものを揺るがす出来事でした。
苦渋の決断 – 現場を離れるということ
医師から告げられたのは、「このまま同じ仕事を続ければ、ヘルニアがさらに悪化し、手術が必要になる可能性が高い」という厳しい現実でした。
同僚や上司に相談すると、皆「身体が資本なんだから無理はするな」と気遣ってくれましたが、その優しさがかえって辛く感じられました。
一番相談しにくかったのは、妻でした。小学生の子供もおり、一家の大黒柱として、安定した収入を途絶えさせるわけにはいきません。
しかし、痛みに顔を歪めながら帰宅する私を、妻は誰よりも心配してくれていました。「あなたの身体が一番大事。道は一つじゃないはずよ」。
その言葉に背中を押され、私はついに臨床現場を離れるという、人生で最も苦しい決断を下しました。
10年以上かけて築き上げてきたキャリア、情熱を注いできた仕事、そして何より担当していた患者さんたちの顔が目に浮かび、言いようのない喪失感と悔しさに襲われました。
 エル
エル「俺は、これからどうすればいいんだ…」。
先が見えない暗闇に、たった一人で放り出されたような気分でした。
模索と葛藤 – 「理学療法士の俺」に何ができるのか?

真っ暗闇の中で見つけた一筋の光
現場を離れると決めたものの、次の一手は全く見えませんでした。
転職サイトを毎日眺めては、ため息をつく日々。医療系の求人は多いものの、そのほとんどが臨床現場での経験を求めるものばかり。
「理学療法士」という国家資格は、私にとって誇りであると同時に、現場を離れた今となっては、もどかしい足枷のようにも感じられました。
ハローワークの相談員の方からは、「全く違う業種に挑戦してみては?」と勧められましたが、これまで培ってきた知識や経験をすべて捨てて、ゼロから何かを始める勇気は到底湧きません。
「患者さんの役に立ちたい」という根本的な想いは、変わらずに心の中にありました。この想いと、理学療法士としての専門知識。この二つを活かせる場所は、臨床現場以外に本当にないのだろうか。
焦りと不安が募る中、まるで出口のないトンネルを彷徨っているような感覚でした。家族の生活を守らなければならないというプレッシャーも重くのしかかり、眠れない夜が続きました。
福祉用具専門相談員という選択肢
そんな八方塞がりの状況だったある日、ふと、訪問リハビリで担当していたある患者さんのことを思い出しました。
彼は進行性の難病を抱え、徐々に身体の自由が利かなくなっていましたが、特殊なクッションや電動ベッドを導入することで、自宅での生活を長く続けることができていました。
その用具を選定し、彼の身体状況や生活環境に合わせて細かく調整してくれたのが、「福祉用具専門相談員」の方でした。
当時の私は、その専門性の高さに感心したことを鮮明に覚えていたのです。「もしかしたら…」。藁にもすがる思いで「福祉用具専門相談員」について調べてみると、驚きの事実が分かりました。
理学療法士や作業療法士などの国家資格保有者は、福祉用具専門相談員指定講習を受けなくても、その業務に従事できるのです。
さらに、その仕事内容は、利用者の身体機能や生活環境を評価(アセスメント)し、最適な福祉用具を選定・提案するという、まさに理学療法士の専門性がダイレクトに活かせるものでした。暗闇の中に、一条の光が差し込んだ瞬間でした。
- 選定相談:利用者の評価から、どのような福祉用具が必要か考える
- 利用計画作成:ケアプランと利用者・家族との相談をもとに利用計画を立てる。
- 適合・取り扱い説明:実際の福祉用具を利用者に合わせて調整する。
- モニタリング:定期的に訪問して、利用状況を確認する。
資格取得と情報収集 – 新たな挑戦への準備
道が見えてからの行動は早かったです。まずは、自分の武器を再確認しました。
- 理学療法士の国家資格: 福祉用具専門相談員としての資格要件を満たしている。
- 12年間の臨床経験:
- アセスメント能力: 患者さんの身体機能、精神状態、家屋環境、介護力などを総合的に評価する力。
- 目標設定能力: ADL(日常生活動作)やQOL(生活の質)の向上というゴールから逆算して、具体的な計画を立てる力。
- 多職種連携の経験: 医師、看護師、ケアマネジャーなど、多くの専門職と連携してきたコミュニケーション能力。
これらの強みを武器に、福祉用具貸与事業所への転職活動を開始しました。
企業研究を進める中で重視したのは、「単なる物売りではなく、利用者の生活に寄り添う姿勢を大切にしているか」という点です。
数社の面接を受け、ある企業の社長の「我々の仕事は、用具を介して利用者の『できる』を増やすことだ」という言葉に強く共感し、入社を決意しました。
面接では、理学療法士としての臨床経験が、利用者のニーズを深く理解し、より質の高い提案に繋がることを具体例を挙げてアピールしました。挫折から始まった転職活動でしたが、自分の新たな可能性に気づき、次第にワク-ワクしている自分がいることに驚きました。
第二のステージへ – 福祉用具専門相談員としての再出発

臨床知識が武器になる!提案の質で差をつける
福祉用具専門相談員として働き始め、私はすぐに「理学療法士の経験は、この仕事の最強の武器だ」と確信しました。
例えば、ケアマネジャーから「歩行が不安定な方に、歩行器を提案してほしい」という依頼があったとします。
以前の私なら、単にカタログから数種類の歩行器を提示するだけだったかもしれません。
しかし、理学療法士としての視点を持つ私は違います。まず、利用者のご自宅を訪問し、なぜ歩行が不安定なのかを評価します。筋力低下なのか、バランス能力の問題なのか、あるいは麻痺の影響なのか。関節の動く範囲(関節可動域)や痛みの有無も確認します。
その上で、家の廊下の幅、敷居の段差、主に生活する部屋の広さなどを細かくチェックします。
その結果、「この方の場合、筋力低下が主因なので、少し体重を預けられる前腕支持型の歩行器が良いでしょう。ただし、寝室の入口が狭いので、折りたたんだ際の幅が〇〇cm以下のモデルが必須です」といった、極めて具体的で根拠のある提案が可能になるのです。
この専門的なアセスメントに基づいた提案は、利用者様やご家族はもちろん、ケアマネジャーからも絶大な信頼を得ることに繋がりました。
提案書作成を効率化!簡単なツール活用術
質の高い提案を心がける一方で、課題も見えてきました。
それは、提案書やモニタリング報告書の作成に時間がかかりすぎることです。特に、利用者の身体状況や選定した福祉用具の機能、レンタル費用の計算などを毎回手入力するのは非効率でした。
そこで私は、理学療法士時代に学会発表などで培ったPCスキルを活かし、業務効率化ツールの自作に取り組みました。具体的には、ExcelのVBA(Visual Basic for Applications)を使い、簡単な入力フォームに情報を打ち込むだけで、提案書の雛形が自動で出力される仕組みを作りました。
【自作ツールの概要】
- 入力シート: 利用者の基本情報、身体機能評価(MMT、関節可動域など)、家屋環境のチェック項目などを入力。
- 商品データベース: 取り扱いのある福祉用具の商品名、機能、サイズ、介護保険レンタル価格などをまとめたシート。
- 自動生成機能: 入力シートの情報に基づき、VBAが最適な福祉用具をデータベースから複数候補抽出し、選定理由や比較表、利用料金の概算を含んだ提案書(Word形式)を自動で作成する。
このツールのおかげで、書類作成時間は以前の3分の1以下に短縮されました。
さらに、提案書には利用者の身体機能や生活動線を視覚的に示すため、レーダーチャートや簡単な見取り図を盛り込みました。
例えば、身体機能の評価項目(筋力、バランス、持久力など)をレーダーチャートで示すことで、どの能力が低下しており、それを補うためにどの用具が必要なのかが一目瞭然になります。
これにより、提案の説得力が格段に増し、利用者やご家族にも「なぜこの用具が必要なのか」が直感的に伝わるようになりました。浮いた時間でより多くの利用者を訪問したり、新しい福祉用具の勉強会に参加したりと、さらに専門性を高める好循環が生まれています。
身体の負担減と心の充実 – 新しい働き方の実現
福祉用具専門相談員の仕事は、デスクワークと利用者宅への訪問が中心です。
重い患者さんを抱えるような肉体労働は一切なくなり、あれほど私を苦しめていた腰痛は、驚くほど改善しました。
定期的に整体に通う必要もなくなり、痛みで夜中に目が覚めることもなくなりました。身体的な健康を取り戻したことは、精神的な安定にも繋がっています。
また、会社の勤務体系がしっかりしているため、残業はほとんどなく、夕方には帰宅できるようになりました。
週末もカレンダー通りに休めます。理学療法士時代は、自己研鑽のための勉強会や患者さんのことで頭がいっぱいで、家に帰ってもどこか仕事モードが抜けきれませんでした。
しかし今は、平日の夜に子供とゆっくり宿題を見たり、週末に家族で公園に出かけたりと、これまで犠牲にしてきた「家族との時間」を存分に味わうことができています。
もちろん、仕事のやりがいも形を変えて存在します。自分が選んだ車椅子で、利用者が笑顔で散歩に出かける姿を見る時。最適なベッドを導入したことで、介護するご家族の負担が減り、「本当に助かりました」と感謝される時。臨床現場とは違う形で、しかし確かに人の生活を支えているという実感が、新たな心の充実感をもたらしてくれています。
転職を考える理学療法士の皆さんへ

あなたの知識と経験は、臨床現場以外でも必ず輝く
もし今、あなたがかつての私のように、身体的な問題や将来への不安から、理学療法士としてのキャリアに悩んでいるのなら、伝えたいことがあります。
それは、「あなたの知識と経験は、臨床現場というステージ以外でも、必ずや大きな価値を持つ」ということです。
私たちは、理学療法士としての教育と臨床経験を通じて、無意識のうちに多くのポータブルスキル(持ち運び可能な能力)を身につけています。
- 課題発見・解決能力: 目の前の患者さんが抱える問題の本質(真のニーズ)を見抜き、それを解決するための最適なアプローチを立案し、実行する力。
- 論理的思考力: 解剖学や運動学といった科学的根拠に基づき、物事を筋道立てて考える力。
- 共感・傾聴力: 相手の痛みや不安に寄り添い、信頼関係を築く力。
これらの能力は、福祉用具専門相談員はもちろんのこと、住宅改修のアドバイザー、介護・医療系企業の企画・営業職、特別支援学校の教員サポートなど、実に様々な分野で求められています。
どうか、「理学療法士=臨床現場」という固定観念に縛られず、少しだけ視野を広げてみてください。そこには、あなたが輝ける新しいステージが、きっと広がっているはずです。
不安を乗り越えるための具体的なアクションプラン
「視野を広げろと言われても、具体的に何をすればいいのか…」と感じる方も多いでしょう。
不安を乗り越え、次の一歩を踏み出すためには、具体的な行動計画が不可欠です。私が実践した、そして皆さんにお勧めしたいアクションプランを以下に示します。
- 自己分析(自分の棚卸し):
- これまでのキャリアで何を得たか(知識、技術、経験)を書き出す。
- 何にやりがいを感じ、何が苦痛だったのかを正直に振り返る。
- 「絶対に譲れない条件」と「妥協できる条件」を明確にする(勤務時間、給与、仕事内容など)。
- 徹底的な情報収集:
- 転職サイトに複数登録し、どんな求人があるのかを幅広く眺める。
- 「理学療法士 転職 臨床以外」などのキーワードで検索し、様々なキャリアパスの事例を読む。
- 興味を持った業界や職種について、書籍やWebサイトで深く調べる。ハローワークの職業相談も有効です。
- 専門家への相談:
- 医療・介護業界に特化した転職エージェントに登録する。キャリアのプロに相談することで、自分では気づかなかった可能性を提示してもらえることがあります。
- 可能であれば、興味のある分野で実際に働いている人の話を聞く機会(OB/OG訪問など)を見つける。
- 行動計画の策定:
- 得られた情報をもとに、「いつまでに、何を、どうするのか」という具体的なスケジュールを立てる。
- まずは履歴書・職務経歴書を更新してみるだけでも、大きな一歩です。
焦る必要はありません。一つひとつ着実に進めていくことが、不安を自信に変える一番の近道です。
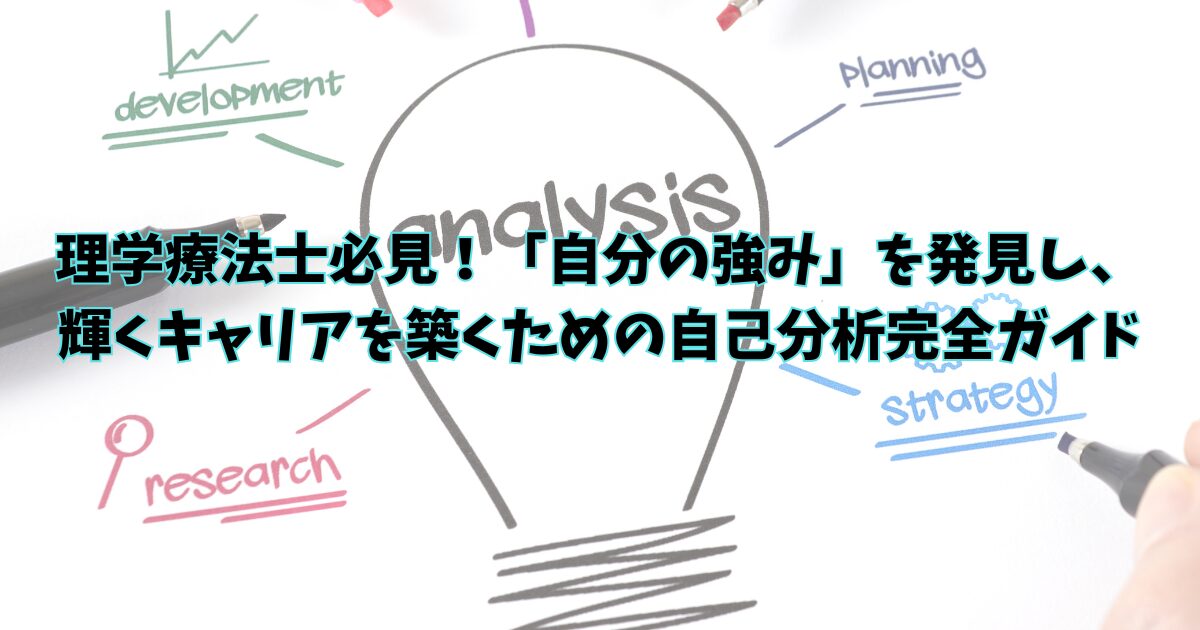
第二のステージは、あなた自身が創り出すもの
転職は、決して逃げではありません。
それは、自分自身の人生とキャリアをより良いものにするための、前向きで戦略的な「転身」です。
私は理学療法士の現場を離れる時、すべてを失うような気持ちでした。
しかし、今なら断言できます。あの時の決断があったからこそ、今の充実した毎日があります。
腰痛という身体的な苦しみから解放され、家族との穏やかな時間を取り戻し、そして何より、「理学療法士だったからこそできること」を武器に、新たな専門分野で人の役に立てている。
この事実は、私に大きな自信と誇りを与えてくれました。あなたの理学療法士としての経験は、金剛石のように硬く、そして多面的に輝く可能性を秘めています。
光を当てる角度を変えれば、これまで見えなかった眩い輝きを放つはずです。どうか、自分自身の可能性を信じて、勇気を持って新たな一歩を踏み出してください。
あなたの第二のステージは、他の誰でもない、あなた自身が創り出すものなのですから。